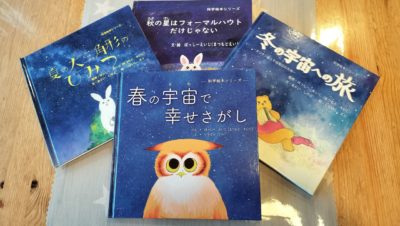今日は雨模様の一日
天候不順な日が多いです
さて昨日は今年のお花見ツアー・その3ということで奈良県の吉野山日帰り弾丸ツアーでした
家を朝4時に出発、23時に帰着というまさに弾丸バスツアーです
日本一の花見の名所、現地には何十台もの大型バスが停まっていました
吉野山は下千本・中千本・上千本・奥千本と四箇所の見所が少しずつ開花時期を変えて楽しめるようになっているそうです
昨日は下から中が見頃を迎えており、週末ほどではないそうですがかなりの人出でした
下・中・上・奥で合計4千本かと思ったら実際には3万本の桜が一帯にあるようで、とても広い範囲に桜の林が拡がっていて、他の桜の名所とのスケールの違いを感じました
世界遺産に指定された史跡も散在しており、桜の咲いていない季節にジックリ散策するのも良いかも知れません